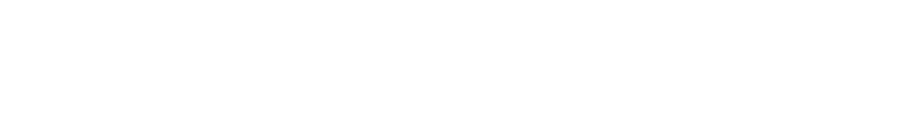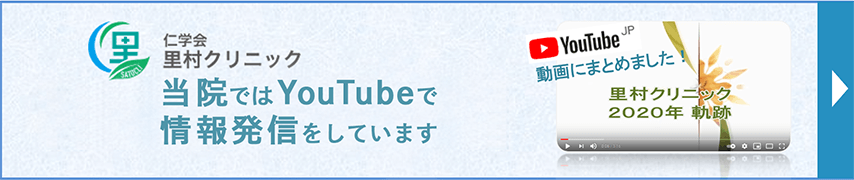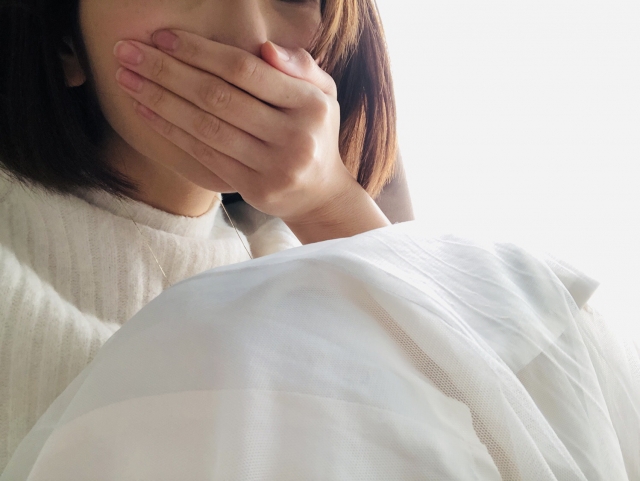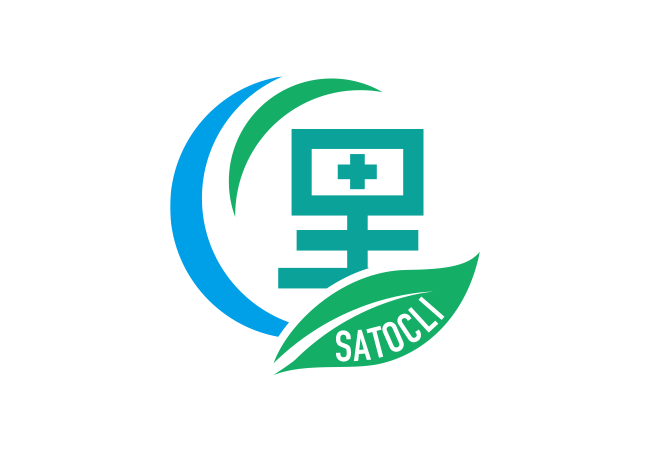2025年8月28日
ヘリコバクター・ピロリ(H. pylori)は、胃の中に生息するらせん状の細菌で、胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんのリスク因子としても知られています。
今回は、ピロリ菌感染の診断・治療・除菌の実際について、最新のエビデンスとガイドラインを基に解説します。
【感染のサイン】
ピロリ菌に感染しても無症状であることが多いですが、胃もたれ・腹部不快感・胃痛などの症状が現れる場合もあります。過去の胃潰瘍歴や萎縮性胃炎がある方は感染の可能性が高くなります。
【検査方法について】
● 非侵襲的検査:
– 血清抗体検査:やや精度は落ちるが、検査が簡便
– 尿素呼気試験:最も精度は高いが、薬剤(PPIなど)を内服していると精度が落ちる。
– 便中抗原検査:費用対効果が高いが、薬剤の影響を受けやすい。
● 内視鏡下検査:
– 迅速ウレアーゼ試験:感度が高く、生検数を増やすとより有効。
– 検鏡法・培養法:専門施設での対応が必要。
【胃がん予防の観点から】
日本の研究(JAMA 2004)では、早期胃がん内視鏡治療後の患者に対して除菌を行ったところ、再発リスクが有意に減少しました(HR 0.339, p=0.003)。
またピロリ菌の感染を放置しておくと胃がんの発生母地となる萎縮性胃炎の範囲が広がってしまいます。そのため、早期に除菌を行うことが重要です。
【除菌治療の実際】
● 一次除菌: ボノプラザン+アモキシシリン+クラリスロマイシン(7日間)
● 二次除菌: ボノプラザン+アモキシシリン+メトロニダゾール
除菌治療をおこなった後、3ヶ月以上経過してから除菌が成功したか確認を行います。除菌に失敗した場合、二次除菌を行います。
ピロリ菌は胃がんのリスクとなるため早期に除菌を行うことが重要です。
少しでも気になる症状があれば、気軽にご相談ください。
院長 稲田 宥治