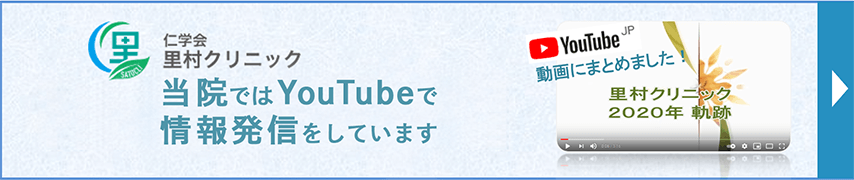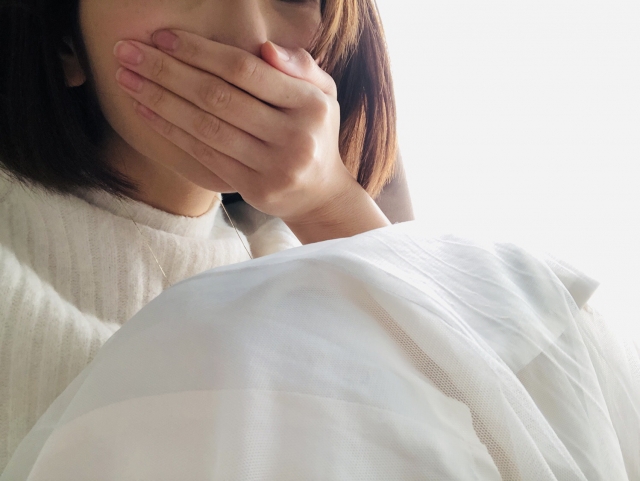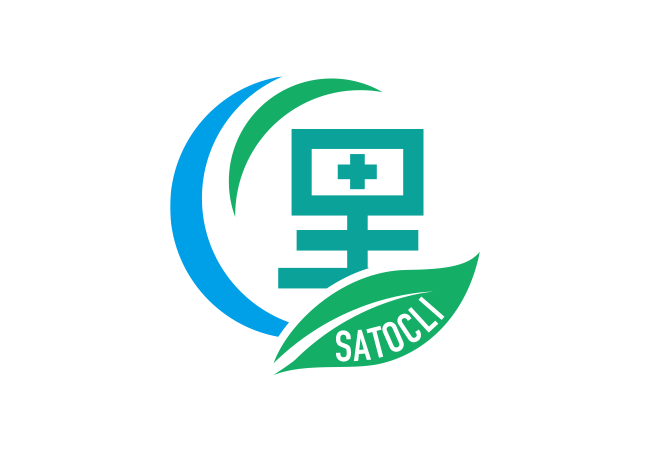2025年10月07日
こんにちは。里村消化器内科・胃と大腸内視鏡クリニック院長の稲田宥治です。
2025年のノーベル生理学・医学賞を受賞された坂口志文(さかぐち しもん)先生をご存じでしょうか。
坂口先生が発見した「制御性T細胞(Treg)」という免疫のブレーキ役は、自己免疫疾患やがん治療だけでなく、実は私たちの専門である胃や大腸の病気(消化器疾患)にも深く関わっているのです。
【🧬 「制御性T細胞」とは?】
制御性T細胞(Treg)は、体の免疫が“暴走”しないようにコントロールする働きを持つ細胞です。
免疫が強すぎると、自分の体を攻撃してしまう「自己免疫疾患」や、慢性炎症を起こす「腸の病気」の原因となります。坂口先生の発見は、まさにこの“免疫のバランス”を理解する大きな一歩でした
【🍽 胃と腸における免疫の働き】
① 自己免疫性胃炎との関係
免疫が誤って自分の胃の壁を攻撃してしまう「自己免疫性胃炎」。
坂口先生の研究チームは、制御性T細胞がこの病気を防ぐ“免疫の守り役”であることを明らかにしました
免疫のブレーキが外れることで、胃の細胞が破壊されてしまう——つまり、免疫のバランスが胃の健康を左右するのです。
② 胃がん治療(免疫チェックポイント阻害薬)との関係
胃がん治療に使われる免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボなど)の効果や副作用にも、制御性T細胞の働きが関わっています。
今後、患者さん一人ひとりに合ったオーダーメイド治療を進める上でも、この研究は大きな鍵になります。
③ 潰瘍性大腸炎・クローン病(IBD)との関係
腸の炎症が続く潰瘍性大腸炎やクローン病(IBD)は、腸内の免疫バランスが崩れることで悪化します。
最新の研究では、制御性T細胞が腸内で正常に働かないと、炎症が止まらないことが分かってきました。
坂口先生の発見は、こうした難治性腸疾患の新たな治療法開発にもつながっています。
【🧠 免疫のバランスが「胃腸の健康」を守る】
免疫と聞くと「風邪に強くなる」といったイメージを持たれる方が多いかもしれませんが、実は胃や腸の病気の裏にも免疫の乱れが関係しています。
坂口先生の研究が示した「制御性T細胞の働き」は、これからの消化器医療に欠かせない視点です。
【🏥 当院からのメッセージ】
当院では、自己免疫性胃炎・潰瘍性大腸炎・ピロリ菌感染・大腸ポリープなど、免疫や炎症が関係する病気の診療を行っています。
「胃の調子が悪い」「血便が出る」「お腹が張る」といった症状は、免疫バランスの乱れが原因かもしれません。放置せず、早めにご相談ください。
また、早期発見のための胃カメラ・大腸カメラ検査も随時行っています。
鎮静剤を用いた“眠っている間に終わる内視鏡検査”や、リラックスして準備できる“下剤バー”など、快適に受けていただける環境を整えています。
胃腸の健康を守るために——まずは一度、内視鏡でご自身の胃と腸の状態をチェックしてみませんか?
里村消化器内科・胃と大腸内視鏡クリニック
院長 稲田 宥治