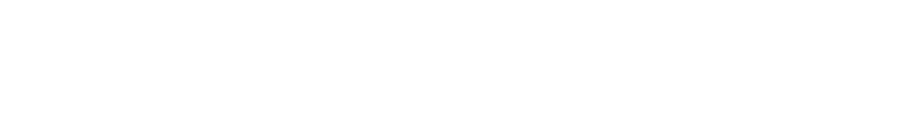食道がんについて
食道がんとは、食道にできるがんのことです。食べ物を口から胃に運ぶ通路である食道は、粘膜、粘膜下層、固有筋層、外膜の4層構造になっています。食道がんは、このうち最も内側の粘膜から発生し、進行するにつれて周りの層やリンパ節、さらには肺や肝臓などの他の臓器にも転移する可能性があります。
初期の食道がんは自覚症状がほとんどなく、健康診断や人間ドックで偶然発見されるケースが多いです。しかし、がんが進行すると、食べ物が飲み込みにくい、胸や背中に痛みがある、声がかすれるなどの症状が現れることがあります。
食道がんは、早期に発見し適切な治療を行うことで、生存率が大幅に向上します。そのため、少しでも気になる症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。当院では、内視鏡検査をはじめ、食道がんの早期発見・早期治療に力を入れていますので、お気軽にご相談ください。
食道がんの初期症状
食道がんは初期段階では自覚症状がほとんどないため、発見が遅れてしまうケースが多い病気です。しかし、注意深く観察することで、いくつかの初期症状に気づくことができます。
食道がんの初期症状
食べ物が飲み込みにくい
初期の食道がんでは、食べ物が食道を通過する際にわずかな抵抗感や引っかかりを感じることがあります。特に、固形物や熱いものを飲み込む際に違和感を感じやすいため、注意が必要です。
胸や背中の痛み
食道がんが進行すると、胸や背中に痛みを感じる場合があります。これは、がんが食道の壁に浸潤したり、周囲の組織を圧迫したりすることで起こります。痛みの程度は、軽度なものから激しいものまで様々です。
げっぷや吐き気
食道がんによって食道の狭窄が起こると、げっぷや吐き気が頻繁に起こることがあります。また、食べたものが逆流することもあります。
体重減少
食道がんが進行すると、食欲不振や食べ物の飲み込みづらさから体重が減少することがあります。
これらの症状は、食道がん以外にも様々な原因で起こる可能性があります。しかし、これらの症状が続く場合は、食道がんの可能性も考慮し、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
食道がんの原因
食道がんは、様々な要因が複雑に絡み合って発症すると考えられています。
主な原因として、以下のものが挙げられます。
喫煙
タバコの煙に含まれる発がん物質が、食道の粘膜を刺激し、細胞の遺伝子を傷つけることで、がん化を促進すると考えられています。喫煙者は、非喫煙者に比べて食道がんのリスクが2~4倍高くなるという報告もあります。
過度の飲酒
アルコールは、食道の粘膜を刺激し、炎症を引き起こすことで、がん化を促進すると考えられています。特に、アルコール度数の高いお酒を大量に飲む習慣がある人は、食道がんのリスクが高くなる傾向があります。
熱い食べ物や飲み物
熱い食べ物や飲み物を頻繁に摂取すると、食道の粘膜が繰り返し熱傷を負い、細胞の遺伝子が傷つき、がん化しやすくなると考えられています。
食生活の偏り
野菜や果物をあまり食べない、塩分の多い食事を好むなど、食生活の偏りも食道がんのリスクを高める要因の一つと考えられています。
肥満
肥満は、食道がんを含む様々ながんのリスクを高めることが知られています。
逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流することで起こる逆流性食道炎を長年患っていると、食道の粘膜が慢性的に炎症を起こし、がん化のリスクが高まると考えられています。
遺伝的要因
食道がんは、家族性集積性を示す場合があり、遺伝的な要因も関与していると考えられています。
これらの要因を複数併せ持つ人は、食道がんのリスクがさらに高くなるため、注意が必要です。食生活の改善や禁煙など、生活習慣を見直すことで、食道がんのリスクを減らすことができます。
食道がんの検査方法
食道がんの検査方法は、主に以下のものがあります。
胃カメラ(胃内視鏡検査)
口や鼻から細い管状のスコープを挿入し、食道の内部を観察する検査です。食道がんの早期発見に最も有効な検査方法であり、がんの有無や大きさ、場所、進行度などを詳しく調べることができます。また、検査中に組織を採取して、顕微鏡でがん細胞の有無を調べる生検を行うことも可能です。
バリウム検査
バリウムという造影剤を飲み込み、X線撮影を行うことで、食道の形状や病変の有無を調べる検査です。内視鏡検査に比べて苦痛が少ないというメリットがありますが、早期がんの発見は難しい場合があります。
CT検査
X線を使って体の断面を撮影する検査です。食道がんの広がりやリンパ節転移、他の臓器への転移などを調べるために用いられます。
PET検査
がん細胞に集まりやすい性質を持つ薬剤を注射し、特殊なカメラで撮影することで、がんの有無や位置、大きさなどを調べる検査です。食道がんの広がりや転移を調べるために用いられます。
これらの検査方法を組み合わせることで、食道がんの診断をより正確に行うことができます。当院では胃カメラ(胃内視鏡検査)を実施しています。
お酒を飲んで、顔が赤くなる人は食道がんになりやすい?
飲酒は食道がんのリスクを高めますが、飲酒後に顔が赤くなる「フラッシャー」と呼ばれる体質の方のほうが、食道がんのリスクが高い傾向があります。
なぜフラッシャーが食道がんになりやすいのかというと、アルコールを分解する過程で発生する「アセトアルデヒド」という物質が関係しています。
アセトアルデヒドには発がん性があり、体内に長く留まるほど、がんのリスクが高まります。フラッシャーの人は、アセトアルデヒドを分解する酵素「ALDH2」の働きが弱いため、アセトアルデヒドが体内に蓄積しやすくなっています。これが、食道がんのリスクを高める要因と考えられています。
つまり、お酒を飲んだ時に顔が赤くなる人は、ALDH2の働きが弱い可能性があり、食道がんのリスクに注意する必要があるということです。
食道がんの時に食べてはいけないもの
食道がんと診断された場合、治療の効果を高め、症状を悪化させないために、食事内容に気を配ることが重要です。特に、食道がんの進行度や治療内容によっては、食べてはいけないものがあります。
食道がんの時に避けるべき食べ物
刺激の強い食べ物
香辛料を多く使った辛い料理、酸味の強いもの、塩分の多いものは、食道の粘膜を刺激し、炎症を悪化させる可能性があります。カレーライス、キムチ、柑橘系の果物、漬物などは控えましょう。
硬い食べ物
硬い肉や野菜、せんべい、フランスパンなどは、食道を通過する際に負担がかかり、痛みや出血を引き起こす可能性があります。柔らかく調理するか、小さく切って食べましょう。
熱い食べ物や飲み物
熱い食べ物や飲み物は、食道の粘膜を傷つけ、炎症を悪化させる可能性があります。熱いスープやお茶、コーヒーなどは、冷ましてから摂取しましょう。
アルコール
アルコールは、食道の粘膜を刺激し、がんの進行を促進する可能性があります。治療中は、禁酒することが望ましいです。
炭酸飲料
炭酸飲料は、胃酸の分泌を促進し、逆流性食道炎を悪化させる可能性があります。
これらの食べ物は、食道がんの症状を悪化させるだけでなく、治療の妨げになる可能性もあります。食道がんと診断された場合は、医師や栄養士に相談し、適切な食事指導を受けるようにしましょう。
当院では、食道がんの診断・治療に豊富な経験を持つ医師が、患者様一人ひとりの症状に合わせた治療法をご提案いたします。食道がんの症状でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。