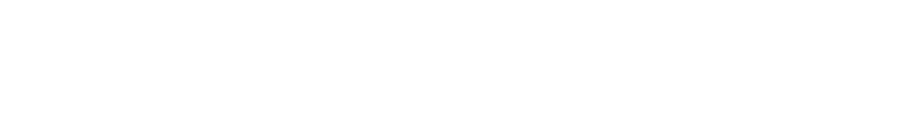ピロリ菌除菌について
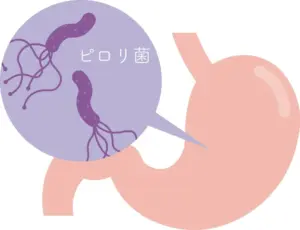
ピロリ菌は、胃の粘膜に生息する細菌です。多くの人が感染していますが、ほとんど自覚症状はありません。しかし、ピロリ菌に感染したまま放置すると、胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、さらには胃がんのリスクが高まることが知られています。
ピロリ菌は、胃酸の中でも生きられるという特殊な能力を持った細菌です。この菌が胃の粘膜に感染すると、炎症を引き起こし、胃もたれや胃の痛み、吐き気などの症状が現れることがあります。また、長期間にわたって感染が続くと、胃の粘膜が萎縮し、胃がんのリスクが高まります。
ピロリ菌の除菌は、胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんの予防に非常に重要です。当院では、患者様一人ひとりの状態に合わせたピロリ菌除菌療法を行っております。
ピロリ菌の感染経路
ピロリ菌の感染経路は主に経口感染です。つまり、口からピロリ菌が体内に入ることで感染します。
具体的には、不衛生な水や食べ物を摂取したり、感染者と食器を共有したりすることで感染する可能性があります。特に、幼少期に感染するケースが多いとされています。
ピロリ菌除菌の流れ
ピロリ菌の除菌治療は、大きく分けて以下の3つのステップで行われます。
1.検査
ピロリ菌に感染しているかどうかを検査します。
検査方法はいくつかありますが、当院では主に以下の4つの検査方法を採用しています。これらの検査方法の中から、患者様の状態に合わせて最適な方法を選択します。
胃カメラ(胃内視鏡検査)

内視鏡を用いて、直接胃の中を観察し、組織を採取してピロリ菌の有無を調べる検査です。
胃の粘膜の状態を詳しく確認できるため、胃炎や胃潰瘍などの有無も同時に診断できます。
ピロリ菌の除菌のためには胃カメラが必要です。
尿素呼気試験
ピロリ菌が尿素を分解する際に発生するガスを測定することで、感染の有無を調べる検査です。
検査薬を服用し、息を採取するだけの簡単な検査で、痛みや不快感はほとんどありません。
内視鏡検査に比べて、患者様の負担が少ない検査方法です。
血液検査
血液中のピロリ菌に対する抗体の有無を調べる検査です。
採血で検査を行います。
便検査
便中のピロリ菌の抗原を検出する検査です。
手軽に検査でき、患者様の負担が少ない検査方法です。
2.除菌治療

検査の結果、ピロリ菌に感染していることが確認された場合は、除菌治療を行います。
除菌治療では、プロトンポンプ阻害薬と2種類の抗生物質を組み合わせた薬を、1週間服用していただきます。
3.除菌判定
除菌薬の服用後、約1ヶ月後に、再び検査を行い、除菌が成功したかどうかを判定します。
ピロリ菌除菌中に食べてはいけないもの
ピロリ菌除菌中は、胃に負担をかけないよう、食事に気を配ることが大切です。
特に、以下のものは控えるようにしましょう。
- 刺激物
香辛料を多く使った辛い料理、カレー、わさび、唐辛子などは胃を刺激するため、控えましょう。 - 脂っこいもの
天ぷら、揚げ物、脂身の多い肉などは消化に悪く、胃に負担をかけるため、控えましょう。 - 酸味の強いもの
柑橘類、酢の物、梅干しなどは胃酸の分泌を促進するため、控えましょう。
これらの食品を完全に避ける必要はありませんが、摂取量を控える、あるいは症状を見ながら調整することが重要です。
ピロリ菌除菌中に飲んではいけないもの
ピロリ菌除菌中は、胃に負担をかけないように、飲物にも注意が必要です。
- アルコール
アルコールは胃の粘膜を刺激し、炎症を悪化させる可能性があります。また、除菌薬の効果を弱める可能性も指摘されています。 - カフェイン
コーヒー、紅茶、緑茶などに含まれるカフェインは、胃酸の分泌を促進し、胃を刺激します。 - 炭酸飲料
炭酸飲料は胃を膨張させ、不快感や消化不良を引き起こす可能性があります。 - 刺激の強いジュース
オレンジジュースやグレープフルーツジュースなど、酸味の強いジュースは胃酸の分泌を促進し、胃を刺激する可能性があります。
除菌期間中は、これらの飲み物を控えるか、量を減らすように心がけましょう。代わりに、水や麦茶、ノンカフェインのお茶など、胃に優しい飲み物を摂取するようにしましょう。
ピロリ菌の除菌でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。