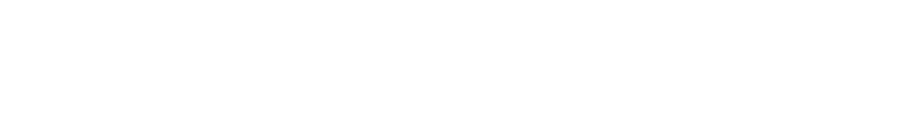膵臓がんについて
膵臓がんは、膵臓にできる悪性腫瘍です。膵臓は、胃の後ろに位置する長さ約15cmほどの臓器で、消化液を分泌する外分泌機能と、血糖値を調節するホルモンを分泌する内分泌機能を担っています。
膵臓がんは早期発見が難しく、初期段階では自覚症状が現れにくく、症状が現れた時にはすでに進行しているケースが多い病気です。また、膵臓は胃や腸などの臓器に囲まれているため、画像検査などでも発見が遅れてしまうことがあります。
膵臓がんは、男女ともに増加傾向にあり、特に高齢者に多い病気です。また、喫煙や糖尿病、慢性膵炎などの生活習慣病もリスク因子として挙げられます。
膵臓がんの初期症状
膵臓がんは初期段階では自覚症状が現れにくいことが特徴ですが、進行するとともに以下のような症状が現れることがあります。
腹痛・背部痛
膵臓は胃の後ろにあるため、がんが大きくなると胃や背中を圧迫し、痛みを感じることがあります。特に、食後や夜間に痛みが増すことがあります。
黄疸
黄疸は、皮膚や白目が黄色くなる症状です。膵臓がんが胆管を圧迫すると、胆汁の流れが悪くなり、黄疸が出ることがあります。
体重減少
がんの進行により、食欲不振や消化吸収障害が起こり、体重が減少することがあります。
疲労感
がん細胞との闘いや栄養不足などにより、強い疲労感を感じることがあります。
食欲不振
膵臓の機能低下やがんによる圧迫感などにより、食欲不振が起こることがあります。
吐き気・嘔吐
膵臓がんが十二指腸を圧迫すると、吐き気や嘔吐が起こることがあります。
糖尿病
膵臓がんがインスリンを分泌する細胞を破壊すると、糖尿病を発症することがあります。
膵臓がんの原因
膵臓がんの明確な原因は、まだわかっていません。しかし、いくつかの要因が膵臓がんのリスクを高めることが知られています。
喫煙
喫煙は膵臓がんの最も重要なリスク因子の1つです。喫煙者は非喫煙者に比べて、膵臓がんになるリスクが2~3倍高くなるといわれています。
糖尿病
糖尿病は、膵臓がんのリスクを1.5~2倍高めるといわれています。
慢性膵炎
慢性膵炎は、膵臓に炎症が慢性的に続く病気です。慢性膵炎があると、膵臓がんのリスクが10~20倍高くなるといわれています。
肥満
肥満は、膵臓がんを含む多くのがんのリスクを高めることが知られています。
高脂肪食
高脂肪食は、膵臓がんのリスクを高める可能性が指摘されています。
家族歴
膵臓がんの家族歴がある人は、膵臓がんになるリスクが高くなります。
加齢
膵臓がんは、加齢とともにリスクが高くなる病気です。60歳以上で発症することが多く、80歳代がピークです。
これらのリスク因子をすべて避けることは難しいかもしれませんが、禁煙や食事の改善、適度な運動など、生活習慣の見直しによって膵臓がんのリスクを減らすことは可能です。
膵臓がんの検査方法
膵臓がんの検査方法は、いくつかあります。まず、問診で症状や既往歴などを伺います。その後、血液検査、画像検査、病理検査などを組み合わせて診断を行います。
血液検査
血液検査では、腫瘍マーカーと呼ばれる、がん細胞が作り出す特定の物質を測定します。膵臓がんでは、CA19-9、CEA、DUPAN-2などが腫瘍マーカーとして用いられます。ただし、これらの腫瘍マーカーは、膵臓がん以外の病気でも上昇することがあるため、確定診断には至りません。
画像検査
画像検査では、膵臓の状態を画像で確認します。腹部超音波検査、CT検査、MRI検査、PET検査などがあります。
腹部超音波検査
簡便で苦痛のない検査ですが、膵臓の位置や周囲の臓器の状態によっては、病変が見えにくいことがあります。
CT検査
X線を使って体の断面を撮影する検査です。膵臓がんの大きさや形、周囲の臓器への浸潤などを詳しく調べることができます。
MRI検査
磁気を使って体の断面を撮影する検査です。CT検査よりも、膵臓がんと正常な組織との区別がつきやすいという利点があります。
PET検査
がん細胞に集まる性質のある薬剤を注射し、その分布を画像化する検査です。がんの転移を調べるのに有用です。
病理検査
病理検査は、膵臓がんの確定診断に最も重要な検査です。細胞診や組織診で採取した細胞や組織を顕微鏡で観察し、がん細胞の有無を調べます。細胞診は、細い針を刺して細胞を採取する検査で、組織診は、内視鏡などを用いて組織を採取する検査です。
これらの検査を組み合わせて、膵臓がんの診断を行います。
膵臓がんと膵癌の違い
「膵臓がん」と「膵癌」は、どちらも同じ病気を指す言葉で、膵臓にできる悪性腫瘍のことです。
ただし、厳密に言うと、「膵癌」は膵臓に発生するがん全般を指すのに対し、「膵臓がん」は膵臓の特定の部位、例えば、消化酵素を運ぶ管である主膵管や側膵管などに発生するがんを指す場合があるというわずかな違いがあります。
膵臓は、食べ物を消化するための消化酵素を生成したり、血糖値を調節するインスリンを分泌したりと、体の重要な機能を担っています。そのため、膵臓にがんが発生すると、消化不良や糖尿病などの症状が現れるだけでなく、がんが進行すると、周囲の臓器や血管、リンパ節などに転移し、生命にも関わる深刻な病態を引き起こす可能性があります。
一般的には、「膵癌」と「膵臓がん」は同じ意味として扱われることが多く、患者さんにとってはどちらの表記であっても、膵臓がんについて正しく理解し、早期発見・早期治療に繋げていくことが重要です。
当院では、膵臓がんの診断・治療に豊富な経験を持つ医師が、患者様一人ひとりの症状に合わせた治療法をご提案いたします。膵臓がんの症状でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。