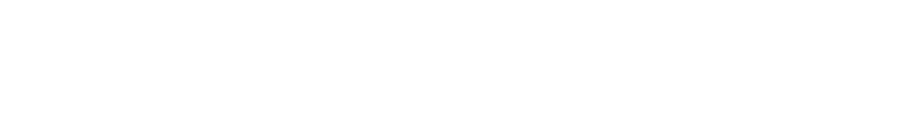機能性ディスペプシアについて
機能性ディスペプシアとは、胃の痛みやもたれなどの症状があるにもかかわらず、検査をしても胃潰瘍やがんなどの異常が見つからない病気です。以前は「神経性胃炎」や「慢性胃炎」などと呼ばれていましたが、近年では「機能性ディスペプシア」という病名で呼ばれることが多くなりました。
内視鏡検査で異常が見つからないため、「気のせいなのでは?」「大したことないのでは?」と思われがちですが、決してそんなことはありません。機能性ディスペプシアは病気であり、日常生活に大きな支障をきたすこともあります。
機能性ディスペプシアの症状
機能性ディスペプシアの症状は人によって様々ですが、主に以下のようなものが挙げられます。
胃もたれ
食後にもたれる感じがしたり、胃が張った感じがする
胃の痛み
みぞおちのあたりに痛みを感じる
早期満腹感
少し食べただけでお腹いっぱいになってしまう
吐き気
吐き気がする、または実際に吐いてしまう
食欲不振
食欲がなく、食事量が減ってしまう
げっぷ
げっぷがよく出る
これらの症状は、ストレスや疲労、食生活の乱れなどによって悪化することがあります。また、症状が長引くことで、不安や抑うつなどの精神的な症状が現れることもあります。
機能性ディスペプシアの原因
機能性ディスペプシアの原因は、まだ完全にはわかっていませんが、以下の要因が複合的に関わっていると考えられています。
胃の運動機能の低下
胃の動きが悪くなると、食べ物が胃に滞りやすくなり、胃もたれや膨満感などの症状が出やすくなります。
胃酸分泌の異常
胃酸の分泌が多すぎたり少なすぎたりすると、胃の粘膜が刺激され、痛みや不快感を感じることがあります。
内臓知覚過敏
胃が通常よりも刺激に敏感になっている状態で、わずかな刺激でも痛みや不快感を感じやすくなります。
ヘリコバクター・ピロリ菌感染
ピロリ菌は胃の粘膜に炎症を起こす細菌で、機能性ディスペプシアのリスクを高める可能性があります。
ストレス
ストレスは胃の運動や分泌機能に影響を与え、症状を悪化させることがあります。
食生活の乱れ
脂肪分の多い食事や刺激の強い食事、不規則な食事は、胃に負担をかけ、症状を悪化させることがあります。
喫煙
タバコに含まれるニコチンは胃酸の分泌を促進し、胃粘膜を傷つけるため、症状を悪化させることがあります。
機能性ディスペプシアの検査方法
機能性ディスペプシアは、胃の痛みやもたれなどの症状があるにもかかわらず、内視鏡検査では異常が見つからない病気です。そのため、他の病気を除外するために、いくつかの検査を行う必要があります。
主な検査方法には、以下のようなものがあります。
問診
症状や生活習慣、既往歴などを詳しく伺います。
胃カメラ(胃内視鏡検査)
食道、胃、十二指腸の内部を観察し、炎症や潰瘍、腫瘍などがないかを確認します。
血液検査
貧血や炎症の有無などを調べます。
ピロリ菌検査
胃の中にピロリ菌がいるかどうかを調べます。
これらの検査結果を総合的に判断し、機能性ディスペプシアと診断されます。
機能性ディスペプシアにおすすめの食事メニュー
機能性ディスペプシアの症状を和らげるには、食事内容に気を配ることが大切です。
ここでは、おすすめの食事メニューと、避けるべき食品についてご紹介します。
おすすめの食事メニュー
- 消化の良いものを食べる
おかゆ、うどん、豆腐、白身魚、鶏むね肉など - 胃に優しい調理法を選ぶ
煮る、蒸す、焼くなど - 少量ずつ、よく噛んで食べる
一度にたくさん食べると胃に負担がかかります。 - 規則正しく食事をとる
食事のリズムを整えることで、胃の働きを正常に保ちます。 - 水分をこまめに摂る
水分不足は消化不良の原因になります。
避けるべき食品
- 脂肪分の多いもの
揚げ物、脂身の多い肉、バター、生クリームなど - 刺激の強いもの
香辛料、コーヒー、炭酸飲料、アルコールなど - 消化の悪いもの
食物繊維の多いもの、もち、ラーメンなど
当院では、機能性ディスペプシアの診断・治療に豊富な経験を持つ医師が、患者様一人ひとりの症状に合わせた治療法をご提案いたします。機能性ディスペプシアでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。